昭和29年(1954年)に近隣の村と合併して「市」となった黒石市は、 人が集まり、仕出屋、床屋、美容院などが立ち並び、お菓子屋は30 軒ほどもひしめく町でした。そんな中、初代の石黒洋三はありったけのお金を集めて街の中心部に「甘洋堂」の看板を掲げ、和洋菓子を作り、お客様に提供してきました。それから約50年。2代目として店に立つ長男の石黒和彦は、令和の時代となったいまも「店は街とともにある」と考え、街の未来に目を凝らしながら、お客様に喜ばれる和洋菓子を作り続けています。

昭和29年(1954年)に近隣の村と合併して「市」となった黒石市は、 人が集まり、仕出屋、床屋、美容院などが立ち並び、お菓子屋は30 軒ほどもひしめく町でした。そんな中、初代の石黒洋三はありったけのお金を集めて街の中心部に「甘洋堂」の看板を掲げ、和洋菓子を作り、お客様に提供してきました。それから約50年。2代目として店に立つ長男の石黒和彦は、令和の時代となったいまも「店は街とともにある」と考え、街の未来に目を凝らしながら、お客様に喜ばれる和洋菓子を作り続けています。


 石黒和彦は幼い頃、甘い香りが漂う工場で黙々とお菓子を作り続ける父洋三の姿を見ていました。時には、カステラやケーキの切れ端、残ったモンブランのクリームをパンにつけておやつに食べながら、ぼんやりと「大人になったら、ここに自分も立っているのかな」と思っていました。
石黒和彦は幼い頃、甘い香りが漂う工場で黙々とお菓子を作り続ける父洋三の姿を見ていました。時には、カステラやケーキの切れ端、残ったモンブランのクリームをパンにつけておやつに食べながら、ぼんやりと「大人になったら、ここに自分も立っているのかな」と思っていました。
その洋三は、手に職を付けようと市内の菓子屋に丁稚奉公した後、青森市の老舗和菓子店「三浦甘精堂」など数軒で修業を積みました。「菓子屋をやるからには、世代を問わず、みんなに愛されるお菓子を作りたい」と考え、洋菓子作りも懸命に学びました。生まれ育った黒石の人達に自分が作るお菓子を食べて欲しいと、昭和44年(1969年)に独立。修業先の店名から「甘」と「堂」を、自らの名前にあり「洋菓子」の字にもある「洋」を加えて「甘洋堂」として、黒石市上町にお店を構えました。時は、高度経済成長。しかし、「地元に何のつてもなく始めた商売を軌道に乗せるため、必死だった」と、和彦はのちに父から聞いています。人を雇うお金もなく、兄弟や親戚が店番に立つ日も多くありました。


 当時、冷蔵機器はまだ普及していなかったため、ケーキなどの生菓子は常温でも日もちするバタークリームが多く用いられていました。黒石市内に菓子屋がひしめく中、新規参入した小さなお店を知ってもらいたい。そして、子どもも大人も喜び、食べた時に思わず笑顔になるお菓子を作りたい。そんな思いから、店を興して2年ほど後、思い切って高額な冷蔵機器を導入し、生クリームを使ったケーキを作り始めると、修行時代から構想を練っていたお菓子を商品にしようと奮闘しました。
当時、冷蔵機器はまだ普及していなかったため、ケーキなどの生菓子は常温でも日もちするバタークリームが多く用いられていました。黒石市内に菓子屋がひしめく中、新規参入した小さなお店を知ってもらいたい。そして、子どもも大人も喜び、食べた時に思わず笑顔になるお菓子を作りたい。そんな思いから、店を興して2年ほど後、思い切って高額な冷蔵機器を導入し、生クリームを使ったケーキを作り始めると、修行時代から構想を練っていたお菓子を商品にしようと奮闘しました。
ケーキを、手軽に持ち歩けて、手土産にも使える形にしたらどうか。子どもも大人も喜ぶ味とは、どんな味だろう。大人は香り高いドリップコーヒーを好きな人が多く、子どももお風呂屋さんでコーヒー牛乳をよく飲んでいる…。そう考えて、コーヒー味の生クリームを薄く丸い形のカステラにはさんだ半月型の商品を生み出します。ショーケースに並べてみると、まだ名前を付けていなかった新商品は飛ぶように売れ、お店の屋台骨を支える主力商品になりました。店を興す時から、「2つも3つもいらない。一生のうち一品、皆さまに愛されて名を残すような銘菓を作ろう」と心に決めていた洋三は、この商品を磨き上げて自分の「一生一品」にしようと思いました。
開店から8年ほど経った頃、現在地の黒石市前町に移転。それに伴い、漢字だけの店名では和菓子のイメージが強いと考え、ふと世界地図で目にしたヨーロッパの町の名前をとって「シャロン甘洋堂」と改めました。そして、まだ名前を付けていなかった看板商品にお店を支えてくれることへの敬意を込めて「シャロン」と名付けました。

 「シャロン」の評判は上々でしたが、近隣には市内で名の売れたお菓子屋もあったため、よりお店の知名度を上げようと洋三は品評会への出品を始めました。昭和48年(1973年)の第1回青森県菓子品評会で二色最中が技術奨励賞を、昭和52年(1977年)の第19回全国菓子大博覧会でチーズカステラが名誉金賞を受賞。昭和59年(1984年)の第20回全国菓子大博覧会では銘菓シャロンが内閣総理大臣賞に輝き、地元のみならず全国にその名を知られるようになりました。平成2年(1990年)のおおわに国体(青森県大鰐町で開催)にご臨席された三笠宮寬仁親王殿下に献上すると、八甲田の春スキーにいらした時にもよくお召し上がりいただき、お店にとって大切な思い出の一コマとなっています。
「シャロン」の評判は上々でしたが、近隣には市内で名の売れたお菓子屋もあったため、よりお店の知名度を上げようと洋三は品評会への出品を始めました。昭和48年(1973年)の第1回青森県菓子品評会で二色最中が技術奨励賞を、昭和52年(1977年)の第19回全国菓子大博覧会でチーズカステラが名誉金賞を受賞。昭和59年(1984年)の第20回全国菓子大博覧会では銘菓シャロンが内閣総理大臣賞に輝き、地元のみならず全国にその名を知られるようになりました。平成2年(1990年)のおおわに国体(青森県大鰐町で開催)にご臨席された三笠宮寬仁親王殿下に献上すると、八甲田の春スキーにいらした時にもよくお召し上がりいただき、お店にとって大切な思い出の一コマとなっています。



コツコツタイプの父に対して“自由気質”の和彦は、弘前の高校へと進みました。卒業までに何度か父が体調を崩すことがあり、早めに店に立つことを考えながら経営を勉強したい思いもありました。「大学に行ってみたい」と切り出すと、洋三は否定せず、「行ってみればいい」という返事でした。1年間、札幌で浪人時代を過ごしながらお金が続く限り街に出ては流行を眺め、商品を見て、食べ歩きました。翌年、四国の大学に入学すると、友だちはたくさんできたものの、「自分が学ぶところは大学ではない」と感じ、半年で自主退学。東京の日本菓子専門学校に入学し直しました。

 2年間の専門学校は最低限の時間だけ通い、残る時間はスーパーでのバイトに費やしました。朝の1時間、スーパーで品出しや検品をしてから専門学校へ行き、授業が終わればすぐスーパーに戻る日が続きました。「アルバイトだったけど、電話の応対やメーカーさんとのやりとり、仕入れの値段決めもすべて任されていて、社員並の仕事をさせてもらいました。いま考えれば、よくアルバイトに任せてくれたと思います」。仕入れ、販売方法、商品の見せ方など、学びたかった「経営のイロハ」をこのスーパーの現場で実際に体験できたことになります。店長の奥さんが青森出身だったというご縁もあり、とても可愛がってもらったことをありがたく思っています。
2年間の専門学校は最低限の時間だけ通い、残る時間はスーパーでのバイトに費やしました。朝の1時間、スーパーで品出しや検品をしてから専門学校へ行き、授業が終わればすぐスーパーに戻る日が続きました。「アルバイトだったけど、電話の応対やメーカーさんとのやりとり、仕入れの値段決めもすべて任されていて、社員並の仕事をさせてもらいました。いま考えれば、よくアルバイトに任せてくれたと思います」。仕入れ、販売方法、商品の見せ方など、学びたかった「経営のイロハ」をこのスーパーの現場で実際に体験できたことになります。店長の奥さんが青森出身だったというご縁もあり、とても可愛がってもらったことをありがたく思っています。
「お客様第一」の姿勢をたたき込まれたのも、このスーパーでの仕事でした。天気予報が翌日の急な寒気を伝えた日、白菜を欠品させてしまいました。店長から近くのスーパーや店を自転車で回り、白菜を買い占めて来るよう指示を出されました。「白菜の仕入れ金額は赤字にはなるけれど、お客様が欲しいものをとにかく準備するのが店の使命だと言われ、なるほどと納得しました。僕の経営についての土台は、この時期に作ってもらいました」


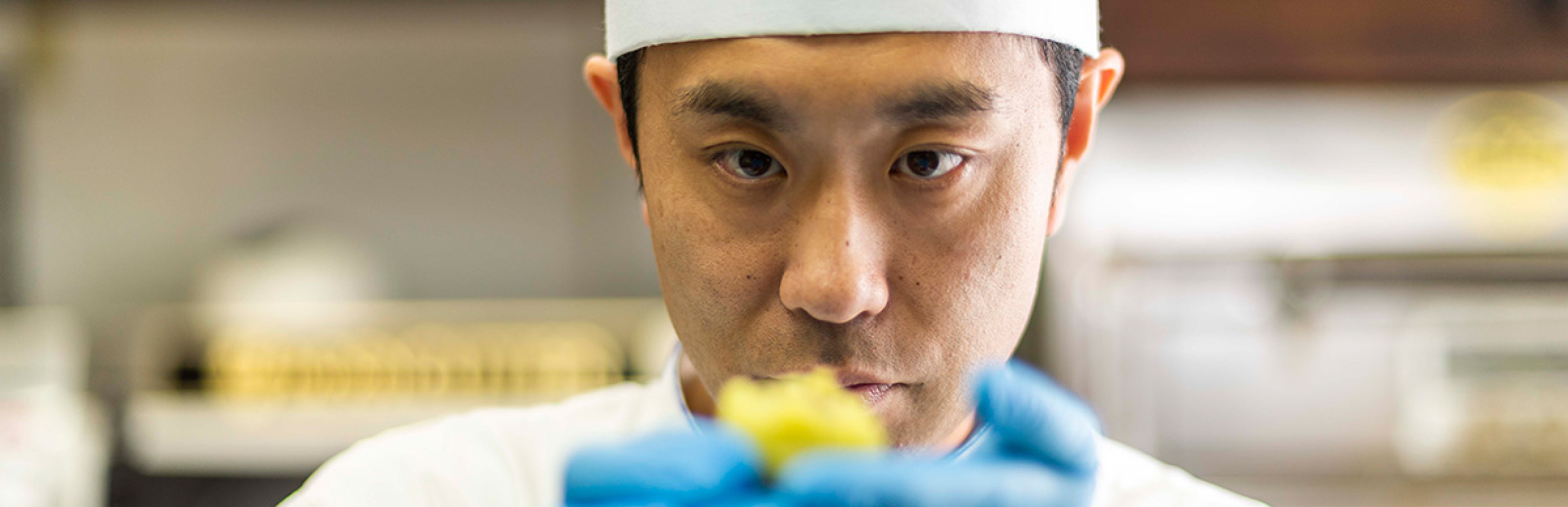
 和彦が専門学校を卒業する頃、父の体調が崩れたことから、帰郷して店を手伝うことにしました。お店に職人として入ってみると、ゼロから店を興すにはどれほどのパワーが必要だったか、店を継続するためにどれほどの苦労があったかを実感し、父への尊敬の念が膨らみました。体調が回復した父は、一緒に工場でお菓子を作りながら、「少しでも商品の格を上げたい」と全国菓子大博覧会への出品を続けていました。「銘菓シャロン」は平成元年(1989年)に名誉無鑑査賞を受賞したほか、「黒石シューロール」など他のお菓子も受賞を重ねていました。父のお菓子は、もしかしたら世界でも通用するのではないか。札幌や東京など大都市で暮らし、消費者の動向や菓子業界の流行を見てきた和彦は、帰郷して間もない頃からそう思っていました。そして、世界的な商品の品質保証と絶大な知名度を誇る「モンドセレクション」に挑戦することを心に決めます。
和彦が専門学校を卒業する頃、父の体調が崩れたことから、帰郷して店を手伝うことにしました。お店に職人として入ってみると、ゼロから店を興すにはどれほどのパワーが必要だったか、店を継続するためにどれほどの苦労があったかを実感し、父への尊敬の念が膨らみました。体調が回復した父は、一緒に工場でお菓子を作りながら、「少しでも商品の格を上げたい」と全国菓子大博覧会への出品を続けていました。「銘菓シャロン」は平成元年(1989年)に名誉無鑑査賞を受賞したほか、「黒石シューロール」など他のお菓子も受賞を重ねていました。父のお菓子は、もしかしたら世界でも通用するのではないか。札幌や東京など大都市で暮らし、消費者の動向や菓子業界の流行を見てきた和彦は、帰郷して間もない頃からそう思っていました。そして、世界的な商品の品質保証と絶大な知名度を誇る「モンドセレクション」に挑戦することを心に決めます。
「モンドセレクション」を選んだことには理由があります。審査基準はお菓子の味や見た目だけではなく、情報開示や商品の食べ方、合う飲み物、商品の歴史や作り手の思いなど、商品にまつわるあらゆるもののクオリティに及ぶということ。さらに、審査は相対評価ではなく出品した商品そのものへの絶対評価であり、自分たちが商品を磨けば賞に手が届く可能性がある評価基準に挑戦することは、自分たちに必要なことにも思えたからです。

モンドセレクションへの挑戦は、経営の見直しにも役立つと考えました。和彦は平成10年(1998年)に取締役に、8年後には代表取締役となって父から経営を引き継いだ後、組織のあり方や時代に合わせた経営方針の転換の必要性を感じていました。「初代はゼロから会社を興すことに精いっぱいで、職人だけに経営については分からないことも多く、毎日が『どうしよう』の連続だったはず。それを何とか商売が成り立つ形にして手渡してくれたことはありがたいこと。二代目の役割は、会社組織を整理整頓し、製造や販売の体制を整え、次の世代が思っていることをスムーズに表現できるように修正し、つないでいくこと」。自分の代から「次」へ引き継ぐため、改革を進めています。

モンドセレクションへの挑戦を決めたものの英語での審査に対応する資料を自社で作れるほど英語に堪能な人材がいるわけではなく、申請に関する手続きなどを代行してくれる東京の企業を見つけて応募しました。初挑戦した平成28年(2016年)の「黒石シューロール」は、銀賞を受賞。翌年、満を持して出品した看板商品の「銘菓シャロン」は見事、金賞を受賞しました。名前もないまま父が世に出した商品は、世界のトップレベルとして認められたのです。地中海のマルタ島で行われた授賞式には、父と連れ立って参加しました。「二人とも初めてのヨーロッパ旅行で珍道中でしたが、授賞式の壇上に上がり、モンドセレクションのパトリック・ド・ハリュー会長からメダルを受け取る父の姿を見た時は嬉しかった」

でも、モンドセレクションには金賞の上に、「最高金賞」があります。「父のシャロンは、もっと磨けるのではないか」との思いがあり、挑戦を続けました。「シンプルなものがいい。お客様に長く愛されているものはシンプルなものが多い。ごちゃごちゃしていたり、食べにくいものはダメだ」という父の思いを守り、味わいのクオリティを上げながら、包装をエコな仕様に変えるなど、考えられる限りの改良を加え、平成31年(2019年)に4度目の挑戦をしました。結果は、最高金賞受賞。ローマで行われた授賞式には、小学3年の息子と一緒に出席しました。「父が内閣総理大臣賞を受賞したのは、自分が小学生の頃。その後、父は町内で何か集まりがあると挨拶をする立場になり、凄い賞をもらったんだなあと、子ども心に思っていました。今回、息子には、お菓子屋でもこういうことができるということを見せたかった」



シャロン甘洋堂が半世紀を迎えるいま、和彦は2代目の役割の一つとして「働き方改革」を進めています。お客様の需要の増加や将来的な展望から、平成20年(2008年)に店舗を拡大リニューアルしました。増産態勢を支えようと違う仕事に就いていた弟が加わりましたが、若手従業員が定着せず、悩んだ時期がありました。若い従業員が育たなければ会社は若返りません。
要因の一つに、高度経済成長で「作れば売れた時代」から続く「朝7時から夜まで働いて当たり前」という職人的な働き方にあると考えました。販売担当は8時間勤務で週休2日とするなど、まずは「自分たちの意識」を変えて、働く環境の改善に取り組みました。勤務時間が短くなったことで従業員の仕事量は一時的に減ったように見えたものの、仕事に対するモチベーションや効率が徐々に上がり、手に技術が定着する様子を見て、長い目で育てる方針に間違いはないと思えるようになりました。

 もう一つ、お店の土台を強固なものにするためにも、より多くのお客様に商品を届けられるようインターネットでの情報発信とネット通販にも力を入れています。モンドセレクションに挑戦し始めた頃から、青森県内にもインバウンド(訪日外国人)の波が訪れ、黒石市内でもインバウンド受け入れに対応しようと平成31年(2019年)9月に、民間団体「Knock² World(ノックノックワールド)」が結成されました。和彦は、そのサブリーダーとして活動しています。その年の6月、モンドセレクションの授賞式で渡欧した際は、黒石PR動画の英語版QRコードを添えたカードを持参し、「黒石の宣伝マン」として多くの方に手渡してきました。黒石ねぷたや黒石よされなどのお祭りがあり、りんご園や温泉郷、紅葉山など観光スポットも多い地元黒石を、一人でも多くの方に知っていただき、足を運んでほしいという思いからです。「決して英語が話せるわけではないけれど、地元を盛り上げようという組織のスタートアップに巡り合えたので、長くお世話になっている街のためにできることをしたい。ゼロからお店を立ち上げた父の苦労を経験してみたい気持ちもあります」。70歳を超えてなお、お菓子を作り続ける父や家族、従業員とともに、世界各国から黒石を訪れる人におもてなしをする準備を進めています。
もう一つ、お店の土台を強固なものにするためにも、より多くのお客様に商品を届けられるようインターネットでの情報発信とネット通販にも力を入れています。モンドセレクションに挑戦し始めた頃から、青森県内にもインバウンド(訪日外国人)の波が訪れ、黒石市内でもインバウンド受け入れに対応しようと平成31年(2019年)9月に、民間団体「Knock² World(ノックノックワールド)」が結成されました。和彦は、そのサブリーダーとして活動しています。その年の6月、モンドセレクションの授賞式で渡欧した際は、黒石PR動画の英語版QRコードを添えたカードを持参し、「黒石の宣伝マン」として多くの方に手渡してきました。黒石ねぷたや黒石よされなどのお祭りがあり、りんご園や温泉郷、紅葉山など観光スポットも多い地元黒石を、一人でも多くの方に知っていただき、足を運んでほしいという思いからです。「決して英語が話せるわけではないけれど、地元を盛り上げようという組織のスタートアップに巡り合えたので、長くお世話になっている街のためにできることをしたい。ゼロからお店を立ち上げた父の苦労を経験してみたい気持ちもあります」。70歳を超えてなお、お菓子を作り続ける父や家族、従業員とともに、世界各国から黒石を訪れる人におもてなしをする準備を進めています。


季節のあしらいが暮らしに彩りを添える和菓子に、誕生日やクリスマスなどイベントを盛り上げる洋菓子。店頭には日々、ケーキ類約40種、和洋焼き菓子約30種、和生菓子約10種が並んでいます。家族の大切な日や仲間との楽しい時間のために、デコレーションケーキや贈答用の箱詰めを求めて、お客様がおいでくださることに感謝しています。
和彦は、新商品を出し続ける一方で、「既存の商品の磨き上げ」にも力を入れています。ショートケーキやカステラ、どら焼など、どこにでもあり、お客様が比べることができる商品こそ、「どこよりも美味しい」と言っていただけることが、「シャロン甘洋堂」にとっての喜びだからです。
「思わずにっこり おいしいお菓子」。商売が軌道に乗り、品評会への出品を始めた頃に洋三が考えたこのフレーズは、これまでと、そしてこれからも変わらぬ「シャロン甘洋堂」の羅針盤として企業理念に掲げています。50年間で積み重ねてきた技、職人のこだわり、そしてお客様のたくさんのご愛顧と笑顔を忘れず、次の50年、さらにその先へと、世代を超えて愛されるお店となるよう「おいしいお菓子」を作り続けてまいります。